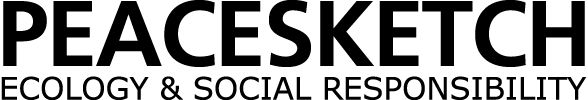昨年7月、デリーがここ数十年で最大の降雨量を記録したとき、私はよく歩いた道路に車が浮いている映像や、私の家と変わらないような家に水が入り込んでいる映像をスクロールして見たことを覚えている。最初は、これもひどいモンスーンのせいだと自分に言い聞かせたが、その規模の大きさに何か納得がいかなかった。
その夜、私は扇風機を止めてベッドに横たわり、天井を見つめながら、これが未来の姿なのかと思った。
外の雨は単なる「天気」ではなく、気候の崩壊が私の世代に何を意味するかを垣間見るものだと思うと、眠れないほどだった。後になって、私が感じていたことには気候不安という名前があることを知った。
気候不安は西洋の言葉ではない
ガーディアン』紙の記事や心理学雑誌に載っているような、遠い西洋の言葉のように聞こえる。しかし、私のような若いインド人にとって、この言葉はもはや抽象的なものではない。私たちは、ビハール州で何千人もの死者を出す熱波、ヒマーチャル州で家屋を破壊する季節はずれの雨、デリーの息苦しい冬、そしてオーブンの中に入ったような夏を受け継ぐ世代なのだ。
このことはあまり語られないが、実は私たちの多くが静かに恐怖を感じている。古い世代とは異なり、私たちにはこうした出来事を「神の御業」や「自然の猛威」として片付ける余裕はない。私たちは、学校の壁には気候科学が、携帯電話の画面には気候災害が映し出されて育ってきた。原因と結果は痛いほど明らかだ。
私にとって、気候不安は奇妙な形で現れる。気温45℃の日にエアコンをつけるたびに、罪悪感にさいなまれる。
きれいな空気が権利ではなく、特権であるかもしれない世界で子供たちを育てることを夢見ることに意味があるのだろうか?
氷河が溶けているにもかかわらず、政府や企業がグリーンウォッシュを続けていることへの怒りと、個人として何をやっても十分ではないかもしれないという諦め。
常に恐怖の状態;
この絶え間ない恐怖の中で生きるのは疲れる。そしてさらに悪いのは、それを取り巻く沈黙だ。インドではすでに精神衛生に関するタブーがたくさんあり、気候不安はそのような稀な会話にすら登場しない。友人とこの話をしようとすると、気まずい笑いが返ってきた-“Yaar, don’t think so much. Sab theek ho jaayega “と。
しかし実際は、何も恐怖を感じることはない。この恐怖が存在しないふりをすることは、私たちをさらに孤立させるだけだ。このスパイラルの中にいるのは自分ひとりではないことはわかっているが、沈黙がそう思わせることもある。
しかし、その重苦しさにもかかわらず、私の不安は愛から来るものであることを否定することはできない。私が育ったデリーの冬への愛。霧は、毒に汚染された空気ではなく、心地よいセーターとチャイを意味していた。祖父が自ら植えたマンゴーの木、子供の頃に泳いだ川、かつて地滑りの代わりに平和を約束した山々への愛。
気候への不安は恐怖だけでなく、私たちが大切にしているものを守りたいという切実な願いでもある。自分が受け継いだ世界は、自分が受け継ぐことのできる世界ではないかもしれないと知ることである。
名前を付けて検証する。
だからこそ、気候不安について語ることは重要なのだ。なぜなら、私たちがその不安を口にすることで、それが正当化されるからだ。私たちは、この恐怖は弱さやメロドラマではなく、すでに進行している危機に対する合理的な反応であることを思い出す。恐怖を共有することで、私たちは連帯感を見出すことができる。そしてそれを認めるとき、私たちはそれを絶望にではなく、行動に移すことができる。それが、より強力な気候政策を求めることであれ、草の根運動を支援することであれ、単に目をそらすことを拒否することであれ、一つひとつの行動が重要なのだ。沈黙は不安を深めるだけだ。会話は、不安を集団の力に変えることができる。
若いインド人として、私たちに選択の余地はない。気候変動は、私たちが年をとり、豊かになり、賢くなるのを待っているのではない。気候変動は、私たちが暮らす都市と、私たちが想像する未来を再構築しているのだ。私たちが自分自身のために、そしてお互いのためにできることは、気候変動が私たちをどのように感じさせているのかを話し合うことだ。なぜなら、無視してもそれはなくならないからだ。そして、もしかしたら、そう名づけることが、それと闘うための第一歩なのかもしれない;